僕の体には、いくつもの刺し傷がある。
15年ほど前、僕はドッペルゲンガーに出会った。
いや、出会ったというより奴は僕を殺しに来たという方が正しいだろう。
巷で囁かれる出会ったら死ぬという都市伝説が、一体どのように起こるものなのか身をもって体験したのだった。
あれは明らかに僕で、僕は奴だった。
それは虫の声が耳に心地よく響くようになったばかりの真夜中のことだった。
当時住んでいたアパートの間取りは1LDKで、リビングの奥に寝室があり、寝るときはいつも寝室のドアは開けたままにしていた。
ベッドから体を起こすと薄暗い常夜灯の明かりもあり、割とはっきりとリビングの先の玄関を仕切るドアまで見える。
いつものように寝室のベッドで彼女の隣に寝ていた僕は、玄関扉の鍵が開くカチャンという音に目を覚ました。
数秒の時間が空き、続いてもう一度、カチャン…。
玄関扉の鍵は防犯のため、ドアノブの上下にひとつずつあった。
何事かと顔を起こし、隣で寝ている彼女を見てからデジタル時計に目をやると、午前1:30を少し過ぎた頃だった。
聞き間違えかとリビングに目を戻すと、リビングと玄関を仕切るドアがゆっくりと開いていく。
半開きになったドアを凝視していると、向こう側のドアノブを握る手がはっきりと見えた。
なぜか不思議と恐怖を感じることはなく、僕はドアの向こうにいるであろう人間の行動を冷静に見ているのだった。
入ってきた男は痩せぎすで、緩いウェーブのかかった長髪の男だった。
長い髪と薄暗い明かりのせいで顔までは見えなかったが、男には確たる目的があるかのように歩き出し、キッチンの前で足を止めた。
薄暗いとはいえ僕の姿は見えているはずなのに、こちらを気にする素振りはまるでない。
それどころか、シンクの下にある扉を開けて一本の包丁を取り出した。
男の手に握られた包丁は薄暗い部屋の中で、鈍い光を弾いていた。
男がこちらに向き直り、一歩、また一歩と近づいてくる。
僕の上に跨り、両手で握った包丁の狙いを定めたその瞬間、僕は確かに見た。
男は僕だった。
どうしてそれまで気付かなかったのだろう…?
特徴的な緩いウェーブは、母親譲りのクセっ毛だった。
僕は布団から目だけを出し、じっと男の顔を見ていた。
次の瞬間、鋭い痛みと硬い金属の感触が僕の胸に突き刺さった。
男は再度両手を振り上げ、力任せに包丁を振り下ろす。
硬い肋骨に阻まれた刃先は、三度目の殺意を腹部に振り下ろす。
包丁は大した抵抗もなく、僕の腹部の中に飲み込まれていった。
男の目と、一連の行動には一切の迷いや躊躇いなど微塵も感じられなかった。
振り上げては振り下ろし…振り上げては振り下ろし…
もう一度、もう一度、もう一度…。
何度目のことだろう…
僕の意識と視界が突然切り替わった。
僕は無表情で自分を見つめる男の上に跨り、狂ったように刃物を振り下ろしている。
自分の家で彼女の隣に寝ている知らない男に、言いしれない怒りと殺意を感じていた。
包丁は血にまみれ、男が掛けている布団には黒い染みがじんわりと広がっている。
胸や腹を何度刺されても顔色一つ変えず、呻き声一つあげないその男に、薄気味悪いものを感じていた。
長い前髪が流れて男の顔がはっきりと見えたとき、背中にゾクリとする冷たい悪寒が走った。
腕の中で血管が凍りつく感覚とでもいうのだろうか、指一本動かすことが出来なかった。
それはまるで、血の通っている人形のような目をしていた。
男は僕だった。
自分の体に突き刺さる刃物ではなく、ただ静かに僕の目だけを見ていた。
そしてまた視界と意識が切り替わる。
僕は口から血のあぶくを吐きながら、僕を殺そうとする男の行動をなんの抵抗もせずにただずっと見ていた。
僕の上で激しく暴れる男の顔は、やはり無表情だった。
あれだけ激しく動いていたのに、息一つ切らしていない。
湿り気を帯びて重くなった布団を、一心不乱に突き刺していた。
そしてまた切り替わる。
もう何度そうしたのだろうか。
無表情で僕を見上げる男の目から、ゆっくりと光が失われていく。
やがて鈍い光の反射もなくなったとき、僕は何度かの深い呼吸をして、馬乗りになった男の上から下りた。
その手と握られた包丁からはテラテラと、黄色い脂肪の欠片まじりの血液がゆっくりとフローリングの床に零れ落ちる。
切り替わる。
男が最後に僕の腹部に深く突き刺した包丁をゆっくりと抜いて、ひどく怠そうな仕草でベッドを降りた。
そのときの僕には、男の行動を観察する意識はなく、眼球は表面に男を映すだけの透明のビー玉のように思えた。
男は包丁をシンクに投げ捨て、手を洗い、置いてあったコップに水を汲んで一気に飲み干した。
それからリビングを通り過ぎ、何事もなかったかのように玄関から出て行った。
僕は思った。
隣に眠る彼女は無事だった。
まるで初めからそこにいないかのように、男は無関心だった。
彼女は無事だった…
二人の僕の中を行ったり来たりした一人分の僕の意識はそこで途切れたのだった。
目を覚ましたのは6年後だった。
夜そのものを凍てつかせてしまいそうな冬の深夜、僕は無機質な病室の中で一人、目を覚ました。
はじめはそこが何処だか解らなかった。
見たこともない風景と乾いた空気に、そこが病室と認識するまでかなりの時間がかかった。
自分が病院のベッドの上にいると気付いて、直ぐにナースコールに手を伸ばす。
思うように動かない体よりも、伸ばした腕が枯れ枝のように細くなっていたことに目を疑った。
混乱する思考を必死に束ねて、叫びだしたい衝動を必死に抑えた。
返事のないナースコールを連打する僕の指はゴツゴツと骨ばって、まるで他人の指だった。
「…もしもし?」
十数回のコールで返ってきた看護師の声には、緊張と恐怖がはっきりと見て取れた。
「手が!僕の手が!!」
限界だった。
暗い部屋に独り、自分の体に起こっている尋常ならざる事態に動転し、僕はほとんど泣きながら叫んでいた。
そうすることでほんの少しだけ、現実から目を逸らしたり、問題を先送り出来るような気がしていた。
「××さん!?××さんですか!?
目を覚まされたんですか!?」
同じことを繰り返し叫ぶ僕に、僕と同じくらい動揺した看護師の女性は、
直ぐに行きますから!と叫んで若い男性の医師を同伴して、雷雨のような足音を鳴らしてやってきた。
どれくらいそうしていただろう…?
明かりの点いた部屋の中でパニックを起こしていた僕に、大丈夫…大丈夫だからね…
まるで赤ん坊をあやすように背中を摩る看護師の声が、意識に寄り添い、心地良さを感じ始めた頃
親や兄弟、その他の親族が真夜中の病室に集まっていた。
それからはさらに理解が追い付かなかった。
たった数ヶ月会わなかっただけで、めっきり老け込んでしまっている父と母
若々しかった兄には無かったはずの白髪があり、叔父の顔にはいくつもの皺が刻まれていた。
声にならずに泣き崩れる祖母、良かった…かった…と泣きながら僕を抱きしめる母。
母や祖母に限らず、集まった親族はみな同じように涙を流していたが、窓に映った見覚えのないガリガリの男が自分だと認識したとき
愕然とした気持ちが、驚きや恐怖を吹き飛ばした。
それはまるで生気のない老人の顔だった。
そして僕は、入院して6年の歳月が流れていることを知らされた。
それからの数日は目まぐるしかった。
毎日行われる様々な検査、僕を一目見ようと病室を訪れるたくさんの医師や看護師たち。
友人たちの来訪がひと段落ついた頃、二人の見知らぬ男たちが病室を訪れた。
訝しがる僕に二人は手帳を提示し、6年前に僕の身に起きた事件を担当した刑事だと名乗った。
この刑事たちの説明は、やっと落ち着きを取り戻しかけていた僕にとって、とても衝撃的なものだった。
凡その説明はこのようなものだった。
その日、彼女と同棲を初めて1年ほど経った頃、僕は意を決してプロポーズをした。
彼女は涙を流してそれを受け入れ、このままではいけないと、その日のうちに過去の清算を済ませようとしたのだった。
同棲前から浮気をしていた彼女は、相手に連絡を取り、約2年に及ぶ相手との関係の解消を、婚約を理由に持ち掛けた。
相手の男は、遊びのはずだった彼女に対していつの間にか執着し、婚約を阻止するため彼氏である僕にすべてを話し、婚約を破棄させてやると脅した。
僕がそれを知ることになれば全てが終わると焦った彼女は、なんとか男の説得を試みようと僕が眠りにつくのを待って男に呼び出されるままにそっと部屋を抜け出した。
深夜ということもあり、まず来客などありえないこと、鍵を閉める音で僕を起こさないために無施錠で外出したのだった。
彼女がアパートを出るのを確認したその隙に、男は僕と彼女が同棲するアパートの玄関から侵入し、寝室で一人眠る僕の上に跨り、胸や腹を複数回滅多刺しにした。
抵抗がなくなり、反応がなくなったのを確認して男はアパートを後にした。
呼び出された彼女は不安からか、相手の男の携帯に何度も電話を掛けるが、一向に連絡がつかない。
諦めてアパートに戻ってみると、ベッドの上で血まみれになっている意識のない僕を発見。
泣いて取り乱しながらも119番通報をして救急車に乗り込み、病院へと付き添ったそうだ。
病院に着いた時にはすでに心肺は停止していたらしく、かなり危険な状態で、助かる見込みはほとんどなかったという。
そんな状態から、救急隊や医師たちの必死の救命措置で奇跡的に息を吹き返したそうだ。
しかし脳に血液が回らなかった時間が長かったせいか、その後6年間僕の意識が戻ることはなかった。
刑事たちの話す言葉は、とてもゆっくりとした丁寧な口調ではあったが、その目にははっきりと憐みが浮かんでいた。
その話し方はまるで、小さな子供におとぎ話を読んで聞かせるように落ち着いたものだったが、僕にはまるで理解が出来なかった。
そして、覚えている限りでいいから事件当日のことを話してほしいと付け加えた。
捕まった犯人はすでに刑務所にて服役しているが、取り調べから一貫して無罪を主張していたこと。
被害者である僕が、何度も滅多刺しにされているにも係わらず、手や腕に一切の抵抗の跡がないこと。
普段から僕が仕事で留守の時に、何度もアパートに犯人を連れ込んでいたおかげで、部屋中に男の指紋はたくさんあったが
シンクで発見された凶器とみられる包丁には、僕の血液が付着していて洗い流した跡は全くないのに、犯人の指紋どころかDNA、
手袋などを使用した形跡が全く見られなかったことなどを聞かされた。
話を聞きながら僕の頭は混乱に混乱を極めた。
僕の記憶とまるで違う。
彼女が浮気?
そういえば意識を取り戻してから、一度も彼女に会っていない。
胸の傷を指でなぞりながら、僕は自分の記憶に残っていることをありのままに話した。
明らかに刑事たちは落胆した顔だった。
自分が自分を殺しにやってくるなんて、事件の後遺症から悪い夢をみてたのだろう。
何度も繰り返される同じ質問に、何度も同じ答えを繰り返す。
陽が落ちかける頃、まるで無駄足だったと、あからさまに不機嫌な態度を隠す様子もなく二人は病室をあとにした。
犯行の動機としては十分なのかもしれない。
僕は刑事たちから聞かされた事件の話を、一つ一つ思い出して考えてみたが、何日経っても僕の記憶が間違っているとは思えなかった。
なんの根拠にもならないが、ついさっき起きた出来事のように生々しさがあり、記憶には未だ体温が残っていた。
それに、すでに終わっている事件について、わざわざ刑事が聞き込みに来るなんてことがあるのだろうか…?
多少の記憶の混乱はあったが、それは時間とともに改善する可能性があると、僕は無事に退院することが出来た。
特に大きな支障をきたすようなこともなく、問題なく日常生活を送ることが出来るだろうとのことだった。
実家に戻った僕がなんの不自由もなく日常生活に慣れ始めた頃、真相を知るために彼女に連絡を取ろうと電話を掛けてみた。
虚しくコールされる呼び出し音には誰の気配もなく、何度掛けてみても繋がらなかった。
しかしその日の夜、彼女の番号から掛け直されてきて、彼女の番号はすでに他人の番号になっていたことを知る。
なんの手がかりも得られなかった。
僕は彼女の実家に向かうことにした。
彼女の実家と僕の実家は飛行機の距離で、幸いにも事件で肩身の狭い思いをしている様子はなかった。
しかしアポなしで来てしまったことと、自分たちの娘が原因でそれなりに大きな事件になってしまったことなどを考えると
呼び鈴を鳴らす手が固まり、何度も押すのを躊躇った。
日曜の午前中ということもあり彼女と御両親は在宅だった。
モニターに映る僕の顔を見るや、外れそうな勢いでドアが開き、驚く僕の目の前で二人揃って土下座した。
「娘が馬鹿なことをしたせいでとんでもないことになってしまった!生きていて良かった!目を覚ましてよかった…」
震える声で涙を流し、玄関の冷たい三和土に、何度も頭を擦り付けながら、深い謝罪を繰り返すのだった。
僕は事件から6年の時間が経過していることで、どこか他人事のように感じていること、ご両親も知らなかったことで
二人にはなんの落ち度もないことなどを強調し、彼女に事件当時のことを聞かせてもらいに来ただけだと、本来の目的を告げた。
僕にそれ以上の他意はないことを理解したのか、二人は2階にいた彼女を呼んできてくれた。
僕の突然の来訪に、彼女は目を見開いて言葉を失っていた。
両親以上に繰り返される謝罪が終わり、やっと泣き止んだ頃に彼女の口から聞けた話。
その日、彼女はやはり相手の男の呼び出しに応じるために、僕が眠りについてから静かにアパートを抜け出した。
男が指定する場所に行ってはみたが、待てど暮らせど肝心の本人が来ない。
電話を掛けたり、メッセージを送ってみても何の返信もなかったために、一度アパートに帰って男からの連絡を待とうと思ったという。
部屋の中は特に変わった様子もなく、ベッドの中で静かに寝息を立てている僕を起こさないようにと、そっと隣で寝たそうだ。
男からの連絡にすぐに対応できるようにと、ずっと気を張っていたそうだが、仕事の疲れもあっていつしかうとうとしてしまったらしい。
その時にキッチンの方からガッシャン!と大きな音が聞こえたそうだ。
何事かと明かりを点けてキッチンを確認してみると、シンクの中に血だらけの包丁があったという。
彼女は怖くなり、混乱しながらも僕を起こそうと寝室に戻ると、目を半開きにして血でぐっしょりと溺れた僕が、ベッドの中で意識を失っていたということだった。
その後は刑事たちから聞かされた話と大して違いはなかったが、決定的な証拠の少なさや杜撰な捜査の矛盾、
警察から聞かされた証言の食い違いなどから彼女は申し訳なさそうに、私は犯人は浮気相手の男とはどうしても思えない…と呟いた。
男は小心者で、殺意をもって人を殺そうとするほど大胆なことが出来る人間じゃないと…。
「それに…」
「それに?」
言葉を詰まらせた彼女に話を促す。
「これは今まで誰にも言ってなかったんだ…。もちろん警察の人にも。
あの日、あなたを乗せた救急車に乗り込もうとしたとき、人だかりの中にあなたの姿があったの…。
一瞬、他人の空似かと思ったんだけど、近所でそんな人見たことないし、聞いたこともなかった。
それに、髪型や服装までまるっきり同じで…血まみれのあなたを見てずっと笑っていたの…。
笑い方までそっくりで。」
僕は彼女の話を聞いて、背筋が凍り付いた。
彼女は続ける。
「夜中に何人もの人がいて、みんな深刻そうな顔をしていたのに、あなただけが笑ってた…。
だけど本当に怖かったのは、誰にもその笑い声が聞こえていないみたいに周りの人も救急隊の人もあなたに無関心だった…。
笑っていたあなたはまるで、私にしか見えていないみたいだった…。今のあなたは、あなたよね…?」
僕は今にも逃げ出したいほどのかつてない恐怖を感じていたが、彼女に言っておかなければいけないことがあったので、なんとか踏みとどまることが出来た。
「たぶん僕だよ。ちゃんと戻ってきた。」
僕は続ける。
「6年間、地獄のような夢を見てたよ。ずっと殺され続けてきた…
そしてこれからは…君の番なんだ。」
凍り付く彼女を見て、僕は嗤った。


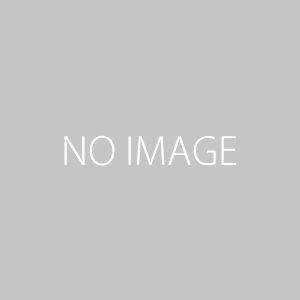
コメント